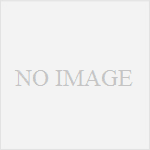商標権の存続期間は「10年」と法律で定められていますが、なぜ10年なのでしょうか?特許や意匠とは異なり、商標は企業や商品の「信用」や「ブランド」を保護する役割があります。そのため、本来であれば半永久的に使用できても不思議ではありません。
しかし、実務では10年ごとの更新が必要であり、最近では5年ごとの分割納付制度や「1年更新」への要望など、制度の柔軟性や課題も注目されています。
本記事では、商標権の存続期間がなぜ10年なのかという制度の背景や他の知的財産権との違い、さらに実務的な対応方法までを、弁理士の視点でわかりやすく解説します。中小企業の方やブランド戦略を検討されている方にとって、商標制度を効果的に活用するヒントが見つかる内容となっています。
商標権の存続期間はなぜ10年なのか?
商標法では、商標権の存続期間は「設定の登録日から10年」と定められています。そしてこの10年ごとに更新が可能で、何度でも繰り返し延長できます。
では、なぜ10年という期間が設定されたのでしょうか?
実は、法律上明確な理由は示されていません。法令の制定過程において、「10年」という数字が選ばれた背景には、以下のような要素が考えられています。
- 商品やサービスのライフサイクルが10年程度で変化する傾向があった
- 企業の活動期間は長期にわたるため、定期的な見直しとして適切
- 権利の放置や死蔵を防ぐために適度な更新制が必要だった
また、国際的にも日本が加盟しているマドリッド協定議定書や商標法条約でも、存続期間は10年と定められており、国際基準にも合致しています。
特許権や意匠権との違い:商標の本質
商標権の存続期間が10年で、かつ何度でも更新可能なのは、他の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)とは大きく異なる点です。
特許や意匠権は「技術やデザインの独占」+「一定期間で公開」
- 一定期間(特許は20年、意匠は25年など)で終了
- 独占と社会への技術開放のバランス
商標権は「信用の保護」が目的
- ブランド価値を守ることが主目的
- 理論上、信用が続く限り、永続的に権利を維持できる
よって、理屈の上では「存続期間がなくてもよい」くらいです。ただし、使われていない商標が市場にあふれると、他者が新たに商標を取得する妨げになります。
そのため、10年という区切りを設け、実際に使っている商標だけが残る仕組みを採っているのです。
商標の更新制度と5年ごとの分割納付制度
長年、商標登録料は10年分をまとめて納付する必要がありましたが、平成8年から「5年ごとの分割納付制度」が導入されました。
これにより、次のような柔軟な対応が可能になりました。
分割納付の概要
| 納付方式 | 費用(1区分) | 特徴 |
|---|---|---|
| 一括納付(10年) | 32,900円 | 最もシンプル。総額は安い。 |
| 分割納付(5年×2回) | 17,200円(前半)+ 後半分未納可 | 最初の5年間だけ使って様子を見ることができる |
たとえば短期間で終了する商品ブランドや、将来的に事業を見直す可能性がある場合、前半5年だけ納付し、更新しないという選択もできます。
この制度は、権利者にとってもコスト管理がしやすく、ビジネスの柔軟性に大きく寄与しています。
ただし、前半5年分を納付した後に10年分を一括納付することはできません。
前半5年分を納付した後は後半5年分を納付して権利を維持します。
つまり、分割納付は権利を長く維持する際に権利維持の費用が一括納付よりも割高になります。
後半5年分を納付したあとは、再び、分割納付するか、一括納付するかを選択できます。
「1年更新制度」への要望とその現実的な課題
一部の中小企業から、「商標権を1年ごとに更新できる制度を導入してほしい」といった要望も出ています。しかし、弁理士としての見解では、これは現実的とは言い難いです。
主な要望の背景
- 製品のライフサイクルが1年未満のものが多い(例:季節商品)
- コストを最小限に抑えたい
- 毎年新しい商標を使って商品展開している
問題点と懸念
- 更新事務が煩雑になり、企業・特許庁ともに負担が増す
- 登録料は1年更新だと、逆に高額に設定される可能性がある
- 商標が頻繁に変更され、消費者に認識されにくくなる
また、模倣や権利侵害があっても、わずか1年間の売上に対する損害賠償は非常に小さく、費用対効果が低くなります。
短期商品の場合は、むしろ権利化せずに次々と新しいアイデアで勝負する戦略も合理的です。
実務的にはどうすべきか?中小企業のための戦略
結局のところ、商標制度をどう使いこなすかはビジネスモデルに応じた判断が必要です。
- 中長期的に継続使用するブランド ⇒ 一括納付で長期的に権利を維持
- 試験的・短期ブランド ⇒ 分割納付で様子を見る
- 超短期サイクルの製品 ⇒ 権利取得せず、市場スピードで勝負
大事なのは、現在の10年更新 or 5年ごとの見直しという制度の中で、賢く権利の維持・更新を選ぶことです。
まとめ:制度を理解し、賢く使うことが成功のカギ
商標権の存続期間が10年である理由は、「制度としてそうなっているから」が正直なところです。ただし、その背景には国際基準、実務的な合理性、ビジネスライフサイクルとの整合性など、多くの要素が関係しています。
1年更新といった極端な制度改正を求めるよりも、今ある制度をうまく活用する方が現実的で効果的です。とくに中小企業にとっては、柔軟な商標管理が競争力につながることを忘れてはなりません。
商標権の存続期間や更新手続きは、制度を正しく理解していれば、無駄なコストを抑えつつ、効果的にブランドを守ることができます。
しかし、ビジネスの内容や展開スピードによって、最適な選択肢は異なります。
「自社の商標は一括納付が良いのか、分割納付が良いのか?」
「使用していない登録商標があるけど、どうすべきか?」
「これから新しいブランドを立ち上げるが、商標登録の必要性は?」
このようなお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の事業に最適な商標戦略をご提案いたします。