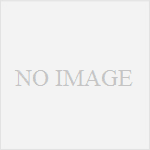商標権侵害に気づいたらどうすればいい?
差止請求・損害賠償・税関申立・刑事告訴など、商標権を守るための正しい対処法を、民事・行政・刑事の視点でわかりやすく解説します。
はじめに|商標権侵害とは?
「自社のロゴやブランド名が勝手に使われている…」
それは商標権の侵害かもしれません。商標権は、商品やサービスの識別力・信用を守るための知的財産権です。侵害行為を放置すると、ブランド価値の低下や顧客の混乱を招くリスクがあります。
本記事では、商標権侵害に対する適切な対処法を「民事上」「行政上」「刑事上」の3つの観点から解説します。
商標権侵害に対する民事上の救済措置とは?
民事手続きは、商標権者が直接侵害者に対して法的手段を講じる最も基本的な対応方法です。
差止請求(商標法第36条)
商標権侵害が認められる場合、侵害行為の差止請求が可能です。
たとえば:
- 模倣品の製造・販売の中止
- ウェブサイトや広告の削除
- 店頭販売の停止 など
裁判所に差止めを求めることで、継続的な被害を防げます。
損害賠償請求(商標法第38条)
実際に被った損害については、金銭的な賠償を請求できます。
損害額の算定には以下の方法があります:
- 侵害者の利益を基準とする算定
- 商標権者の本来得られたであろう利益
- 実際の損害の立証
立証が難しい場合も、法律に基づいた「推定計算」が認められるケースもあります。
信用回復措置の請求
企業の社会的信用が損なわれた場合、謝罪広告や訂正広告の掲載を求めることで、名誉回復を図ることが可能です。
商標権侵害に対する行政上の救済措置とは?
行政的な対応は、侵害品の流通そのものを食い止める手段として効果的です。
税関での輸入差止申立て(知的財産侵害物品の差止)
模倣品が海外から輸入されている場合、税関に対して「輸入差止申立て」を行うことで、侵害商品の国内流通を防止できます。
- 必要書類:商標登録証、商品画像、証拠資料など
- 対象:ロゴ入りの偽ブランド品など
一度登録すれば、税関が自動的に監視してくれるため、特にECサイトなどで流通しているケースに有効です。
公正取引委員会への申告(不正競争防止法)
商標の無断使用が不正競争行為(周知表示混同惹起行為など)に該当する場合、公正取引委員会への申告も選択肢になります。行政機関の勧告や調査を通じて、問題を是正させることができます。
商標権侵害に対する刑事上の救済措置とは?
商標権侵害は悪質な場合、刑事罰の対象にもなります。
刑事告訴による対応(商標法第78条)
侵害者に対して、刑事告訴を行うことで、警察や検察の捜査が入り、刑事処罰が科される可能性があります。
- 個人:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)
- 法人:3億円以下の罰金
刑事告訴の流れ
- 弁理士や弁護士に相談
- 証拠資料の収集(広告、領収書、侵害商品の写真など)
- 警察署や検察庁に告訴状を提出
- 捜査・起訴・刑事裁判へ
特に意図的な模倣品の製造・販売を行っているような業者には、有効な対抗措置となります。
商標権侵害への対処は早期対応がカギ
商標権侵害は、早期に対応することで被害の拡大を防ぐことができます。
放置すれば、消費者の信頼や企業価値に甚大な影響を与えることもあります。
迷ったら弁理士に相談を
- 侵害かどうか判断がつかない
- 差止請求や損害賠償を検討している
- 模倣品を見つけたがどう動くべきか不明
このような場合、まずは商標の専門家である弁理士への相談をおすすめします。
どのような対応が可能か、まずは何をすべきかなどを弁理士がサポートしてくれます。
まとめ|商標権を守るために、今すぐ動こう
| 対応方法 | 内容 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 民事手続き | 差止・損害賠償 | 被害の直接回復 |
| 行政手続き | 税関申立・公取申告 | 流通阻止・行政勧告 |
| 刑事手続き | 刑事告訴 | 厳罰化・再発防止 |
商標権侵害に直面した場合、単に我慢しているとブランド価値の毀損や市場での混乱を招くおそれがあります。
被害を最小限に抑えるためには、民事・行政・刑事の各救済手段を適切に使い分けることが重要です。
侵害が疑われる場合、証拠を早めに収集し、専門家に相談することが最も効果的な第一歩です。