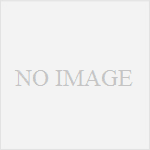「商標を出願したけれど、まだ登録されていない。この段階で誰かに似たような商標を使われたら、どうすればいいの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
以前話題になった「PPAP商標事件」では、商標が未登録の状態で出願人が音楽会社に対して“警告”を行ったことが注目を集めました。実は、商標登録前でも条件を満たせば一定の請求ができる制度が存在します。それが「金銭的請求権」です。
本記事では、知的財産の専門家である弁理士の視点から、「商標権がなくても警告できるのか?」「金銭的請求権とは何か?」「警告を受けたらどう対応すればよいのか?」について、事例を交えながらわかりやすく解説します。
商標を守りたい人、警告を受けた人、いずれにとっても役立つ内容です。ぜひ最後までお読みください。
商標出願中に起きるトラブルとは
商標はビジネスの「顔」であり、ブランドを守るための重要な知的財産です。しかし、出願してから登録が完了するまでには一定の時間がかかります。その期間中に、第三者による商標の使用や類似名称の商標出願といったトラブルが発生することがあります。
例えば、ピコ太郎さんの「PPAP」という言葉が他人により商標出願された事例は記憶に新しいところです。この事例では、商標出願人が音楽会社に対して「警告」を行ったことが話題になりました。果たして、商標権をまだ取得していない段階で、警告することは法的に可能なのでしょうか?
この疑問に答えるカギが、「金銭的請求権」という制度にあります。
金銭的請求権とは?制度の概要と目的
金銭的請求権とは、商標出願後から登録前の期間に、第三者の商標使用によって出願人が損害を受けた場合、その損害を補填するために設けられた制度です。
商標法上は、正式な商標権が設定登録される前でも、「業務上の信用」が第三者の行為により害された場合、登録後に遡って金銭の請求が可能となる仕組みがあります。
この制度の目的は明確です。
- 商標出願人を不当な損害から守る
- 登録を待っている間でも、ある程度の法的保護を与える
ただし、これは無条件で認められるものではありません。要件を満たさない限り、権利の行使(=金銭請求)はできないのです。
商標出願中に「警告」が正当になる条件
商標法では、金銭的請求権を行使するために、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 警告を行っていること
出願の内容を記載した書面などを提示し、相手方に警告を行う必要があります。
→ 単なる口頭での主張やSNSでの発信では要件を満たしません。 - 相手方が警告後に商標を使用したこと
警告の後、相手方が指定商品・指定役務について継続的に商標を使用している必要があります。
→ 警告前の使用は対象外です。 - 出願人が実際に損害を受けたこと
商標使用により、出願人の業務上の信用が損なわれた、売上が減少した等の具体的な損害が必要です。
→ 損害の発生が証明できなければ請求は通りません。
つまり、警告は出せるが、それが有効と認められるかは別問題。この点を理解していないと、無意味な警告をしてしまうリスクがあります。
PPAP事件から考察する、要件を満たさないリスク
「PPAP」商標出願事件では、出願人が音楽会社に対して警告を行いましたが、実際には業務上の損害が存在していなかったと考えられます。
たとえば:
- 出願人自身が「PPAP」で商品やサービスを展開していたわけではない
- 「PPAP」という商標の使用により、出願人が収益を失った証拠がない
このように、上の要件の「出願人が実際に損害を受けたこと」を満たしていないため、仮に商標登録されたとしても金銭的請求権の行使は認められない可能性が極めて高いのです。
このような行動は、法的に無意味であるばかりか、相手企業との無用なトラブルを招く可能性もあるため、戦略的に極めてリスクの高い対応といえるでしょう。
警告された側の冷静な対応方法と注意点
一方、商標出願人から警告を受けた側も、慌てる必要はありません。警告が有効かどうかを冷静に判断すれば、対処できます。
チェックすべきポイントは次の通り:
- その商標は出願中か?登録済みか?
- 警告の内容は書面か?内容証明か?
- 実際に損害が発生した証拠があるか?
これらを精査し、必要に応じて弁理士や弁護士に相談することで、不当な請求やトラブルから身を守ることができます。
重要なのは、「商標出願中」の段階では、まだ正式な権利者ではないという点です。この立場の弱さを利用した圧力に屈する必要はありません。
まとめ
商標を出願中であっても、一定の要件を満たすことで「警告」を行い、後に金銭的請求権を行使できる可能性があります。しかし、そのためには形式的・実質的に厳格な要件をクリアしなければなりません。
今回取り上げた「PPAP事件」では、その要件を満たしていないため、仮に登録されたとしても金銭的請求は難しいと考えられます。
したがって、出願中に他人の行為に困っても、まずは法的根拠を明確にしてから行動することが重要です。一方で、警告を受けた側も、すぐに怯えることなく、冷静に内容を見極めて対処することが求められます。
知的財産の世界では、「正当な権利あってこその警告」です。
商標の出願中に起こるトラブルや、「この警告、本当に正当なの?」といった不安は、専門的な知識がないと判断が難しいものです。
「これってどうなんだろう?」
「ちょっと話を聞いてみたいな」
そう思ったときが、動き出すタイミングかもしれません。
かいせい事務所では、商標に関するご相談を随時受け付けています。
ちょっとしたご質問から、具体的な戦略のご相談まで、お気軽にご連絡ください!