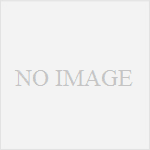特許出願の際、「誰を発明者として記載するべきか?」という問いは、意外にも奥深く、かつ誤解されやすいテーマです。実は、日本の特許法には「発明者」や「共同発明者」の明確な定義が記載されておらず、実務ではその判断に戸惑うケースも少なくありません。
上司がテーマを与えたからといって、必ずしも発明者とは限らず、資金提供者や単なる補助者も発明者に含まれない可能性があります。では、真に「発明者」とは誰なのでしょうか?
この記事では、弁理士の視点から、特許制度における発明者の正しい判断基準と、誤った記載を防ぐための具体例を交えながら分かりやすく解説します。企業の知財担当者はもちろん、研究者・開発者にとっても必見の内容です。
発明者とは?特許法上の定義と実務的な考え方
特許制度において、もっとも根本的かつ重要な存在が「発明者」です。
しかし、意外にも日本の特許法では、「発明者」や「共同発明者」という言葉の明確な定義は設けられていません。
では、実際に特許を出願する際、「誰が発明者になるのか?」という点をどう判断すればよいのでしょうか。
この問いに対し、学説および実務上では次のように考えられています。
「発明者とは、その発明の創作行為に実際に関与した者」
つまり、発明の内容を思いついたり、それを具現化するための技術的工夫をした者が該当します。
ここで重要なのは、「発明者」になれるのは実質的な創作活動に関与した人だけであり、役職や指導・支援の立場は関係ないという点です。
発明者と認められないケース|補助者・助言者・資金提供者
発明に何らかの形で関与していたとしても、発明者には該当しない立場があります。代表的な例を以下に示します。
(例1)単なる管理者
例えば、部下に「こういうテーマで研究してほしい」と指示を出しただけの上司。
これは具体的な技術的着想を与えていないため、発明者とは認められません。
(例2)補助的な作業者
指示に従って実験をしたり、データをまとめるだけの業務に従事した人も、創作性を伴わない作業である以上、発明者とはされません。
(例3)資金提供者・委託者
資金を出したり、設備の提供を行っただけでは、それは後方支援に過ぎません。
あくまでも発明の「アイディア」や「技術的工夫」を出していないため、発明者にはなりません。
これらの事例は、「発明者」という立場が形式的な関与ではなく、実質的な創作行為に基づくことを物語っています。
共同発明者の判断基準とは?2つの重要なステップ
複数人が関与する「共同発明」の場合、誰が共同発明者として認められるかを見極めるには、発明の成立過程を2段階に分けて考える必要があります。
ステップ1:着想の提供
発明に関して「こういう方向性でやってみよう」という新しい着想を提供した者は、その着想が技術的に新規で創造性のあるものであれば、発明者に該当します。
ただし、単に着想を提供しただけで、その後に何の関与もせず他人により具体化されてしまった場合、着想者と具体化者の間に連続的な協力関係がないとして、着想者は発明者とされない可能性があります。
ステップ2:着想の具体化
提供された着想をもとに、それを具体的な技術として実現するプロセスに実質的に関与した者は、当業者にとって自明でない程度の創作性がある限り、共同発明者となります。
このように、単に一部分に関与しただけでは不十分であり、「一体的・継続的な協力関係」の有無が重要な判断ポイントとなります。
職務発明における発明者の認定例
企業においても、発明は日常的に生まれます。では、会社の中での発明行為において、「発明者」が誰なのかをどのように判断するのでしょうか?
以下の例を見てみましょう。
ケース1:社長が直接発明した
→ 社長が実際に着想を出し、技術的な工夫を自ら行った場合は、当然ながら社長自身が発明者となります。
ケース2:社長が指示、社員が発明
→ 社長が「こういう商品を開発せよ」と命じただけで、実際の技術的内容を社員が考案した場合、発明者は社員です。社長は発明者には該当しません。
ケース3:取引先が要望を出し、社員が開発
→ 取引先が「こういう商品が欲しい」と要望を出したとしても、それは発明のきっかけに過ぎません。
それを技術的に実現したのは社員であるため、発明者は社員のみとなります。
これらの例からも分かるように、誰が創作の主体だったのかを見極めることが発明者の認定に直結します。
法人は発明者になれない?自然人に限られる理由
ここで押さえておきたい重要なポイントが一つあります。
「発明者」は必ず自然人(=人間)でなければならない。
つまり、会社などの法人、あるいはAIなどの非自然人は、いかに関与していても「発明者」としては認められません。
特許制度は、発明を生み出した個人の知的努力を保護する制度であるため、発明者の資格は人間個人に限られているのです。
まとめ
「誰が発明者になるのか」という問題は、特許の正当性や権利の帰属に直結する非常に重要な論点です。
形式的な肩書や役職、資金の提供などは発明者の判断に影響を与えず、技術的な創作行為にどれだけ実質的に関与したかが唯一の判断基準です。
企業においても、発明が生まれる現場では、誰がどの部分で創造的な貢献をしたかを明確に記録し、適切な発明者の記載を行うことが、後のトラブル防止にもつながります。
特許法には「発明者」「共同発明者」の明確な定義はない
→ 実務上は「発明の創作行為に実質的に関与した者」が発明者とされる。
発明者にならない典型的な立場
- 単なる管理者(例:テーマを与えるだけの上司)
- 単なる補助者(例:指示通りに実験やデータ処理を行うだけの人)
- 資金提供者・委託者(例:研究資金や設備の提供者)
共同発明者の認定には「着想」と「具体化」の両段階が重要
- 新規な着想を提供し、それが発明に繋がる場合 → 発明者
- 着想を具体的に技術として実現した場合(非自明な工夫) → 発明者
- 両者の間に協力関係がなければ共同発明とは認められない。
職務発明においても、創作の主体が発明者になる
- 社長の指示による社員の発明 → 発明者は社員
- 取引先の要望を元に社員が技術開発 → 発明者は社員のみ
発明者は自然人(人間)に限られる
→ 法人やAIは、いかに関与していても発明者にはなれない。