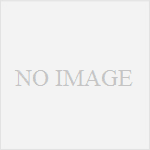創業80年以上の歴史を持つ「二葉屋株式会社」が出願した商標「フタバヤ」。一度は拒絶されたものの、不服審判を経て見事に登録が認められました。
本記事では、商標登録に至るまでの経緯と審査での争点、そして老舗ブランドが商標戦略で勝ち取った逆転劇のポイントをわかりやすく解説します。商標に関わる全ての方にとって、示唆に富んだ実例をお届けします。
二葉屋株式会社とは?
二葉屋株式会社は、東京都中野区に本拠を置く企業で、1941年創業の歴史をもつ老舗です。今回の商標「フタバヤ(FUTABAYA)」は、その屋号をローマ字や漢字、図形を交えて表現したものであり、同社の長年の伝統やブランド力を象徴しています。
審判の概要と手続きの流れ
本件は、2023年10月11日に出願された商標「フタバヤ」が一度拒絶され、不服審判を経て登録が認められた事例です。審判番号は「不服2024-13759」。
審判の流れは以下の通りです:
- 2023年10月11日:商標出願
- 2024年3月15日:拒絶理由通知
- 2024年5月20日:意見書提出
- 2024年7月16日:拒絶査定
- 2024年8月27日:審判請求
- 2025年5月27日:審決(原査定取り消し)
- 2025年6月10日:審決確定


左が本願商標、右が引用商標です。(画像はJ-PlatPatより引用)
審査で争点となったポイント
争点となったのは、既存商標との「類似性」でした。
比較対象となったのは、登録商標第5209272号(以下「引用商標」)。この商標も「フタバヤ(FUTABAYA)」という呼称を含んでおり、小売業務に関する指定役務も近似していました。
拒絶理由として、商標法第4条第1項第11号が適用され、「既存商標と混同するおそれがある」とされたのです。
特許庁が「登録可能」と判断した理由
ここで重要なのは、特許庁の審査官がどのように両商標を分析し、最終的に登録可能と判断したかという点です。
外観と観念の相違
- 本願商標は「赤い円形」「家紋風の図形」「屋葉二」「FUTABAYA」「1941」などから構成され、老舗ブランドの看板を連想させるデザイン。
- 一方、引用商標は緑の四角背景に白抜きのFUTABAYA文字と「フタバヤ」のカタカナを配した図形商標。
→ これらの視覚的構成は大きく異なるため、外観の混同は起きにくいと判断。
呼称の共通性と観念の違い
- 両者ともに「フタバヤ」と呼称される点は共通。
- しかし、「屋葉二」や「FUTABAYA」は「二葉屋という屋号」の意味合いを強く含み、観念的には老舗のブランド名として機能。
- 対して、引用商標の「FUTABAYA」や「フタバヤ」は、特定の観念を喚起しない。
→ 呼称の類似があっても、観念が異なるため混同の可能性は低いと判断されました。
実務上のポイント
商標は「文字の一致」だけでなく、外観や観念、さらには業界での使用実態なども含めて総合的に判断されるという好例です。
商標審決から学ぶブランド保護の重要性
この事例から学べるのは、商標出願においては以下のポイントを押さえることが重要だということです:
① 屋号・創業年・地名の活用
老舗企業のブランディングにおいて、創業年や所在地の地名を商標構成に含めることは非常に効果的です。今回の「NAKANO」「TOKYO」「1941」などの要素が、識別性を高める要因となりました。
② 拒絶後の戦略的対応
拒絶査定を受けても、意見書や補正書の提出を通じて登録への道を開くことが可能です。代理人である弁理士との連携がカギを握ります。
③ 商標の一体性を主張
視覚的・観念的に一体的な印象を与える商標であることを的確に主張することで、他の商標との区別性を明確にできます。
まとめと今後の展望
今回の審決は、伝統ある企業が自社のブランドを守り、商標登録を勝ち取った好例といえるでしょう。
商標審判の過程では、「FUTABAYA」という文字が既存商標と同一であっても、構成の工夫や観念の違いを立証することで、非類似と判断される可能性があることが示されました。
商標とは、単なるロゴや文字列ではなく、企業の歴史、価値、信頼の象徴です。
今後、二葉屋株式会社がこの商標を用いて、より強固なブランド展開を進めることが期待されます。
本記事でご紹介したように、商標登録は単なる申請手続きではなく、ブランドを守るための重要な戦略です。出願前の調査や、拒絶対応、不服審判に至るケースまで、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。
商標の出願をご検討中の方、あるいは拒絶理由通知などでお困りの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
経験豊富な弁理士が、貴社のブランドを確実に保護するため、最適なサポートをご提供いたします。