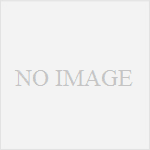商標登録を考える際、気をつけなければならない重要なポイントのひとつが、「識別力」の有無です。特に、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」は、商標法第3条第1項第5号により、識別力がないとして商標登録が拒絶される可能性が高いとされています。
本記事では、実際の審決・判例をもとに、「どこまでなら回避できるのか?」という実務的な観点から、登録可否の境界線を考察していきます。
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とは?
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とは、以下のような極端に単純で一般的な記号を指します。
- 一本の線
- アルファベット1~2文字
- 数字1桁~数桁
- 単純な記号や図形
こうした標章は、単体では商品やサービスの出所を示す力(=識別力)がないとされ、原則として登録が認められません。
実際に登録が認められなかった商標例
以下は、実際に「極めて簡単で、ありふれた」と判断され、登録が拒絶された商標の事例です。
「CQ10」(不服2006-009995)
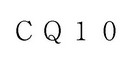
→ アルファベット2文字+数字2桁の構成。
審決では、商品やサービスの品番・等級を示すものと認識され得ると判断され、識別力なしとされました。
「CR-250NN」(不服2007-006439)
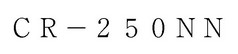
→ ローマ字+数字+ハイフン構成。
これも型式・規格などを示す符号と受け取られる可能性が高く、識別力に欠けるとされました。
「i」(知財高判 平成27年(行ケ)10019)
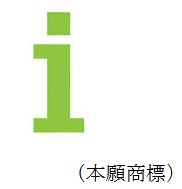
→ セリフ書体や図案的処理が施されていても、一般的な範囲を出ないと判断され、登録不可。
他にも、「<」(不服2003-004385)や「P」(不服2007-029718)といった単一文字・記号についても、図案化の程度が低いとの理由で、登録が認められていません。
登録が認められた商標の傾向
一方で、同じくシンプルな構成でも、一定の独自性や視覚的工夫が加わっている場合は、識別力ありと判断され、登録が認められた例もあります。
「N2H2」(不服2003-007856)
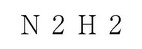
→ ローマ字と数字を交互に配列した構成。
一般的な型番の形式とは異なり、独自性があるとして登録が認められました。
「LJ100」(不服2007-009876)
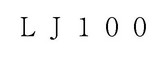
→ アルファベット2文字+数字3桁。
審決では、商品の型番などと認識される実情が見当たらないとされ、識別力ありと判断。
「△」(不服2015-006576、登録第5791747号)

→ 淡い青色で角の丸い正三角形を描いた図形。
単なる三角形ではなく、線の太さや角の処理に独自性があり、識別標識として機能しうると判断されました。
また、「S」(不服2001-18341)や「Z」(不服2004-006408)などの1文字ローマ字であっても、特殊なデザインや図案化により識別力が認められた事例もあります。
登録可否の分かれ目とは?
これらの事例から、商標登録の可否を分ける要素は以下のように整理できます。
| 観点 | 登録不可となる傾向 | 登録可とされる傾向 |
|---|---|---|
| 構成 | 文字1~2字、数字、単純な記号・図形 | 複雑な組み合わせ、非一般的な配列 |
| 使用実態 | 型番・規格・等級と認識されやすい | 商品等の識別標識と認識される |
| 図案性 | 標準文字、図案化の程度が低い | 装飾性が高い、視覚的特徴がある |
| 色彩・フォント | 一般的・無個性 | 色の工夫、独特なフォント使用 |
つまり、たとえ簡単な構成であっても、独自性を加えることで識別力を獲得できる可能性があります。
実務的な対応策とまとめ
「極めて簡単で、ありふれた標章」に該当しそうな商標を出願する際には、以下のような対応を検討するとよいでしょう。
出願前チェックを徹底する
- 商標審査基準だけでなく、過去の審決例・判決例をチェックし、出願予定の商標がそれらと類似していないか確認します。
視覚的特徴を加える
- 図案化(フォント、装飾、図形化)や色彩の工夫を加え、識別力を高めるようにします。
類型化されやすい構成は避ける
- 型番やスペックに見える構成(例:CR-250NN)には注意し、規格表記に見えない独自性のある構成にする必要があります。
拒絶された場合の対応も想定
- 審査で拒絶された場合に備えて、別案の用意や補正の方針もあらかじめ考えておくのが賢明です。
【まとめ】何が良くて、何がダメか?―識別力の境界線を見極めよう
「極めて簡単で、ありふれた標章」の登録可否は、一見単純そうでいて、非常に微妙なライン上の判断が求められます。
特許庁の審査官も審判官も、実際の取引実態や社会通念を踏まえて判断しており、図案のちょっとした違いや使用実態の差が結果を大きく左右します。
結局のところ、何が良くて何がダメなのかは、過去の審決・判例を通じて傾向を掴むことが非常に重要です。
商標出願をお考えの方は、事前調査と専門家による確認をぜひ怠らないようにしましょう。
「自分の商標は登録できるのか不安…」
「どの程度図案化すれば識別力があると判断されるの?」
そんなお悩みがありましたら、かいせい特許事務所へお気軽にご連絡ください。