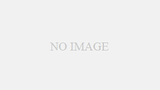企業やブランドにとって、「ロゴ」や「名前」だけでなく、キャッチコピー・サウンド・ブランドカラーといった視覚・聴覚に訴える要素は、消費者との関係を築くための重要な資産です。これらの要素が模倣されたり無断で使われると、ブランドの信頼性や認知度が損なわれてしまう恐れがあります。
そこで注目されているのが、非文字商標(Non-Traditional Trademarks)の活用。近年では、言葉だけでなく、音や色なども商標として正式に登録できるようになり、企業のブランド戦略における「守り」の選択肢が格段に広がっています。
本記事では、キャッチコピー・サウンド・ブランドカラーそれぞれの商標化のメリットや具体的な登録事例、審査のポイント、そして実務上の注意点までをわかりやすく解説します。ブランドを本気で守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
商標の基本と対象範囲の拡大 – 文字だけじゃない時代へ
従来、「商標」と言えば企業名や商品名などの文字情報が中心でした。しかし現在の商標制度は、それにとどまりません。ロゴ、キャッチコピー、サウンド(音商標)、色(色彩商標)といった、より感覚的・視覚的な要素も商標として登録することが可能となっています。
2015年、日本でも非伝統的商標(Non-Traditional Trademarks)として「音」「色彩」「動き」「ホログラム」「位置」などが正式に登録可能になりました。これにより、企業のブランディングの幅は大きく広がり、視覚・聴覚に訴えるマーケティング資産の保護が現実のものとなったのです。
商標権を取得することで、以下のようなリスクを未然に防ぐことができます。
- キャッチコピーの模倣によるブランド毀損
- ブランドサウンドの無断二次利用
- ブランドカラーの模倣による消費者の混乱
- ロゴの一部を改変しただけのデザイン模倣
現代のブランディング戦略において、商標は単なる法的保護ではなく、ブランド価値そのものを守る“盾”となる存在なのです。
キャッチコピーの商標登録:ブランドのメッセージを守る鍵
企業や製品の「顔」となるキャッチコピーは、シンプルで記憶に残りやすい言葉であるほど、他社に真似されやすいという宿命を持っています。実際、短く強い言葉ほど模倣されやすく、商標登録が極めて有効です。
たとえば、資生堂の「一瞬も一生も美しく」は、代表的なキャッチコピー商標です(商標登録第4929296号)。こうした登録によって、他社が似たような表現で市場展開することを防止できるのです。
- 独自性があること(単なる商品説明や一般名詞では不可)
- 識別力があること(消費者がそのキャッチコピーを特定のブランドと認識する)
- 過度に抽象的でないこと
キャッチコピーは、言葉一つでブランドの魂を表現する重要資産。だからこそ、法的な保護が求められるのです。
サウンドの商標化:音で印象を固定するブランディング戦略
Intelのサウンドロゴ(商標登録第5985747号)、あるいは大幸薬品株式会社のラッパ音(商標登録第5985746号)。
これらはすでに「音商標」として商標登録されており、企業の認知度やブランド印象に強い影響を与えています。
日本における音商標の審査基準は明確で、以下のようなポイントがあります。
審査ポイント
- 特定の商品・サービスと結びつく識別性
- BGMやナレーション付き広告音声などは不可
- 実際に音声データとして提出(楽譜・波形データも可)
登録された主な音商標
- 大正製薬「リポビタンD」のCM音(商標登録第5804565号)
- ビックカメラのテーマソング(商標登録第6870956号)
- ペイペイの決済音(商標登録第6939939号)
聴覚に訴えるマーケティング要素は、いまや視覚情報に次ぐ重要資産。音を商標化することで、企業の“音の顔”を守ることができるのです。
ブランドカラーと色彩商標:色で記憶されるブランドになる
「赤といえばコカ・コーラ」「青といえばサムスン」「ピンクといえばバービー」——
このように、特定の色が特定ブランドと強く結びついている例は世界中にあります。日本でも2017年に色彩商標の登録が認められ、より戦略的にブランドカラーを守ることが可能となりました。
登録例
- 株式会社ファミリーマート:緑、白、青の組み合わせ(商標登録第6085064号)
- 株式会社トンボ鉛筆:青、白、黒のバンド(商標登録第5930334号)
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ:濃い緑色と黄緑色の2色バンド(商標登録第6021307号)
審査ポイント
- 色自体に識別性があるか
- 長年の使用実績があること(証拠資料が必要)
- 特定の業界・商品との関連性が認知されていること
色は消費者の記憶に残りやすく、広告やパッケージ、ウェブサイトにおいても統一性を保つことで視覚的ブランド力が強化されます。ただし、相当高い識別力を持たないと審査に合格することは難しいです。
商標戦略を成功させるための実務ポイントと事例紹介
ここまで見てきたように、ロゴだけでなく「音」「色」「言葉」といった感覚的要素を商標登録することが可能です。では、実際にどのように戦略的に登録し、維持・活用していくべきなのでしょうか?
商標戦略の成功ポイント
- ブランド戦略との整合性を取る(感性要素も中長期的にブレない設計を)
- マーケティングと法務の連携(制作段階から法的保護を意識)
- 継続的なモニタリングと更新(5年ごとの使用実績報告が求められるケースも)
登録・維持にかかるコスト例
- 出願手数料+登録費用で合計40,000~60,000円程度/1区分
- 弁理士や商標専門家のサポートは10万円以上のケースも
- 更新費用(10年ごと):38,800円~
登録がゴールではなく、運用が真価を問われるフェーズです。模倣品監視や商標使用のルール化、海外展開時の国際出願(マドリッド協定議定書による)も視野に入れましょう。
まとめ
「キャッチコピー」「サウンド」「ブランドカラー」は、いずれも企業の記憶資産=ブランド資産です。それらを守る最も有効な方法の一つが商標登録です。
視覚・聴覚に訴える非文字商標が制度的に保護されるようになった今、企業にとっては積極的な登録と戦略的な活用が問われる時代となっています。
ブランドの印象が一瞬で模倣され、消費者に混乱を与えるリスクを避けるためにも、「言葉」「音」「色」を戦略的かつ実務的に保護するアプローチが不可欠です。
企業や個人ブランドの競争優位性を築くためにも、「見せる」「聞かせる」「感じさせる」ブランド要素の法的保護を、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
ブランド資産を守るための商標戦略は、タイミングと専門的な判断が鍵となります。
「うちのキャッチコピーやブランドカラーは商標登録できるの?」「音商標の申請ってどう進めるの?」など、具体的なご相談がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。