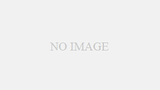インターネットを通じて流通するコンテンツ――たとえば電子書籍、アプリ、音楽ファイルなどの「電子情報財」。これらは形のないデジタルデータですが、商標法の観点では「商品」として扱われるのでしょうか?それとも「サービス」なのでしょうか?
本記事では、電子情報財が商標法上どのように分類されるのかを、法律的な定義や実務の観点、さらには国際的な基準も踏まえて分かりやすく解説します。
電子情報を取り扱う事業者にとっては、商標出願の区分選定に関わる重要なテーマです。デジタル時代のビジネスに欠かせない知識として、ぜひ最後までご覧ください
はじめに:電子情報財の正体とは?
インターネット社会が発達した現代において、私たちは日常的に「電子情報財」に触れています。たとえば、電子書籍や音楽ファイル、スマホアプリ、クラウド上で動くソフトウェアなどがその代表例です。
では、これらの「電子情報財」は商標法の世界では「商品」として扱われるのでしょうか?それとも「サービス」として分類されるのでしょうか?
この記事では、商標法上の「商品」と「サービス(役務)」の違いをふまえ、電子情報財がどのように扱われるかを解説していきます。
商標法における「商品」と「役務」の定義
商標法において「商品」とは、「商取引の目的たりうべき物、特に動産」を指します。具体的には、以下のような物理的なものが該当します。
- 自動車
- 雑誌
- スマートフォン
- 食品など
一方で、「役務(サービス)」とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」をいいます。これは例えば、ホテルの宿泊サービスや、ソフトウェア開発の提供などが該当します。
電子情報財は「商品」か?それとも「サービス」か?
では、プログラムや電子出版物などの「電子情報財」はどうなるのでしょうか?
電子情報財は物理的に存在しない「無体物」です。しかし、現在ではパソコンやスマートフォンなどを通じて広く流通しています。そのため、無体物であっても商取引の対象になりうる場合には、「商品」として扱われる傾向にあります。
ただし、すべての電子情報財が「商品」と見なされるわけではありません。ここで重要になるのが「流通性」という要件です。
「流通性」が鍵:ダウンロードできるかどうか
電子情報財が「商品」として認められるには、実際にユーザーのデバイスにダウンロードされ、保存・管理される必要があります。
例えば、以下のような場合は「商品」として取り扱われる可能性が高いです。
- 音楽ファイルのダウンロード販売
- 電子書籍の販売(PDFやEPUB形式など)
- アプリの配信(ダウンロード形式)
これに対して、以下のような提供方法では、「商品」ではなく「サービス」として分類されます。
- ASP型(クラウド型)ソフトウェアの提供
- ストリーミング配信(保存不可)
- SaaS型の業務支援ツールの利用提供
つまり、「保存が可能であるか否か」が商品とサービスを分ける分水嶺となります。
国際的にも基準は「ダウンロード可否」
国際的にも、電子情報財の商標分類については、「ダウンロードが可能かどうか」によって区別するのが通例です。
- ダウンロード可能な電子情報財 → 「商品」として第9類に該当
- ダウンロード不可な電子情報財の機能提供 → 「役務(サービス)」として第42類などに該当
このように、提供形式に応じて商標区分を適切に選択することが、商標出願の成否を左右する重要なポイントになります。
まとめ:電子情報財は形なき商品にもなりうる
現代では、形のない情報も立派な「商品」として扱われる時代になりました。ただし、その取り扱いは提供方法に大きく依存します。
- 保存可能なダウンロード形式なら「商品」
- ストリーミングやASP型のように保存できないなら「サービス」
という基準を押さえておくことで、商標出願において適切な区分選定ができるようになります。
デジタルコンテンツを取り扱うビジネスにおいては、この区別を誤ると商標登録が無効になったり、思わぬトラブルを招く可能性もあります。商標出願を検討されている方は、弁理士などの専門家に相談することをおすすめします。
電子情報財のように、形のないコンテンツが商品かサービスかの判断は、商標出願において非常に重要です。提供方法によって適切な区分が変わるため、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。
「自社の提供するサービスは第何類で出願すべき?」
「将来的にトラブルにならないように、出願内容を見直したい」
そんなお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。